風邪のメカニズム
- 2021年11月26日
- 読了時間: 2分
更新日:2023年2月2日
西洋医学には「風邪=かぜ」という病名はありません。そして東洋医学では、病の原因を「邪」と考えていて、いくつかの種類と特徴があります。
「風邪=ふうじゃ」「暑邪=しょじゃ」「湿邪=しつじゃ」「燥邪=そうじゃ」「寒邪=かんじゃ」
「風邪=かぜ」の初期症状として、寒気、熱っぽい、喉の痛み、鼻水、頭痛など身体の上部に現れることが殆どです。これは「風邪=ふうじゃ」は上へ移動しやすい特徴があり、症状が現れると「邪」が体内に侵入したことを意味します。簡単に分類をすると、
「風邪+寒邪」=熱はある、汗をかかない
「風邪+熱邪」=熱はなく熱っぽい、喉痛
風邪をひいて発熱した時というのは、身体が、体内に侵入した「邪=ウイルス・細菌」と戦っている最中です。熱の高さで「邪」の強さや体力を考えることができます。そして発熱は悪いモノと考えがちですが、免疫力をあげてくれる良い奴と言えることができます。
子供の頃に、弱った狐の写真が載っている記事を読んだことがあります。その記事には、野生動物は年に1度ほど風邪をひくと書かれてました。発熱した動物はどうするか?と言いますと、じーっと耐えて熱が下がるのをひたすら待つのだそうです。
外敵に襲われる心配もあるのに辛いですよね(>_<)
自分の身体が、武器(白血球)を使用して体内に侵入したウイルスと戦います。ウイルスに勝った時には回復へと向かい、自分の免疫力もあがるという仕組みなのです。これが本来の生体メカニズムであり人間のカラダも同じなのです。
発熱は決して悪いことばかりでなく、免疫力アップという産物があることも事実なんです。
※因みにここでは重症疾患を除きますね。
風邪の初期段階で鍼灸院へ訪れる方は少ないですが、幼少期から薬の服用が多かった私は、鍼灸治療と出会って病院へ行かなくなりました。定期的な治療で回復力も高くなり、今では風邪をひいたり、寝込むことが全くありません。
現代に暮らす私たちにとって西洋医学は大切なものですが、予防医学という観点から、ご自身にあった治療法をみつけられると良いと思います。

前の記事
Homepage

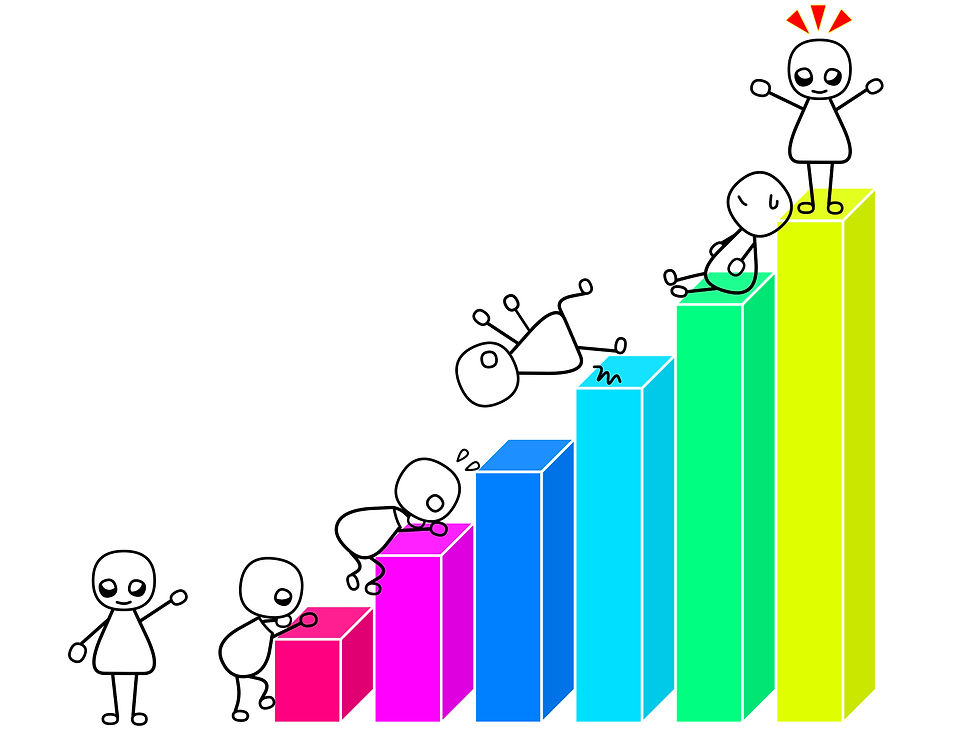

コメント