辞について
- 2024年6月13日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年9月27日
数年前に易経繋辞上伝の「辞=ことば」について書かれている一部を解釈したことがあります。
自分の解釈が本当に解釈と言えるのか?と思って内心に留めておきましたが、数年後に読み返えしたく書き残しておこうと思いました。
まぁ〜このブログ読む人も少ないので思い切ってという感じです(◔‿◔).。
(原文)
子曰 書不尽言 言不尽意
然則聖人之意 其不可見乎
子曰 聖人立象以尽意 設卦以尽情偽
繋辞焉以尽言 変而通之以尽利
鼓之舞之以尽神
孔子曰く、書は言を尽くさず、言は意を尽くさず
然らば即ち、聖人の意それ見るべからざるか
孔子曰く、聖人は象を立てて意を尽くし、卦を設けて情偽を尽くし
辞を繋げて言を尽くし、変じこれを通じて、もって利を尽くし
これを鼓しこれを舞し、もって神を尽くす
(小林解釈)
文章は、言いたいこと全てを書き表すことはできません。話す内容は、心で想っている全てのことを話していません。では相手の想いを理解することはできないのでしょうか?
イメージや例えを使って心の内を表現することはできますし、現象や行動で嘘や真(まこと)を判断することもできます。更には言葉を使い好ましい状況になる道を伝えることができ、その道に進み生じた変化が新たな縁へと繋がっていきます。
このような状態になれば、心に強い意志と深い集中力が自ずと生まれ、これらが全身を満たした時、人知を超えた結果がもたらされるのでしょう。
この内容は現代の出来事に置きかえることができます。
例えば、何回もメールのやり取りで理解ができないのに、少し話しただけでわかることってありませんか?また書物は、想像して読む必要があることが多々あります。
会話や発表などの話す内容には、あえて言わないことや言えないことが多かったりしますし、話すこと自体が苦手な方もいます。
つまり、「辞=言葉」(文語・口語)には限界があるということが理解できます。
ここからは私の考えになりますが、「辞=言葉」になる前には、「想い」の期間があると思っています。その「想い」を抱えて発したモノが「辞=言葉」ですから、言葉の意味だけを捉えるのではなく、言葉に隠された「想い」に対して意識し、理解しようとする自分の「想う」気持ちが大切と考えています。
自分の強い「想い」を持ち続けることで、次第にその「想い」が相手に届くようになり、深い所でその「想い」が繋がった時に、驚くような結果が現れるのではないか?と、今の私はこのように解釈しています。

鍼灸治療をしていても、これに重なる部分があります。
検査で異常なし・要手術などと診断された方が、なかなか思う様な結果が得られないことがあります。治療中に話す私の「辞」は毎回違っても、私の「想い」に変化はありません。諦めるという言葉はないという意味です。
徐々に患者さんの言葉は変化していき、ある日突然「スッキリ感が得られた!」と驚かれることがあります。
このスッキリ感は、患者さんの言葉を借りると「突然よくなった!」「〇〇の症状がない!」「数値が下がった!」「治ったかも?!」などに当たりますが、これがまさに易経に書いてある「人知を超えた結果」なのかもしれません。
人間の「想い」には、言葉にできない奥深さがあり、読んだり聞いたりする「辞」より、目に見えず耳で聞こえない「想い」の方が重要ということなのかもしれません。
よりよい人間関係を築くために、更には大切な方との関係を深めるためにも心掛けたいと思います。
豊かさある心を持っていたいですよね。
前の記事
HP
blog
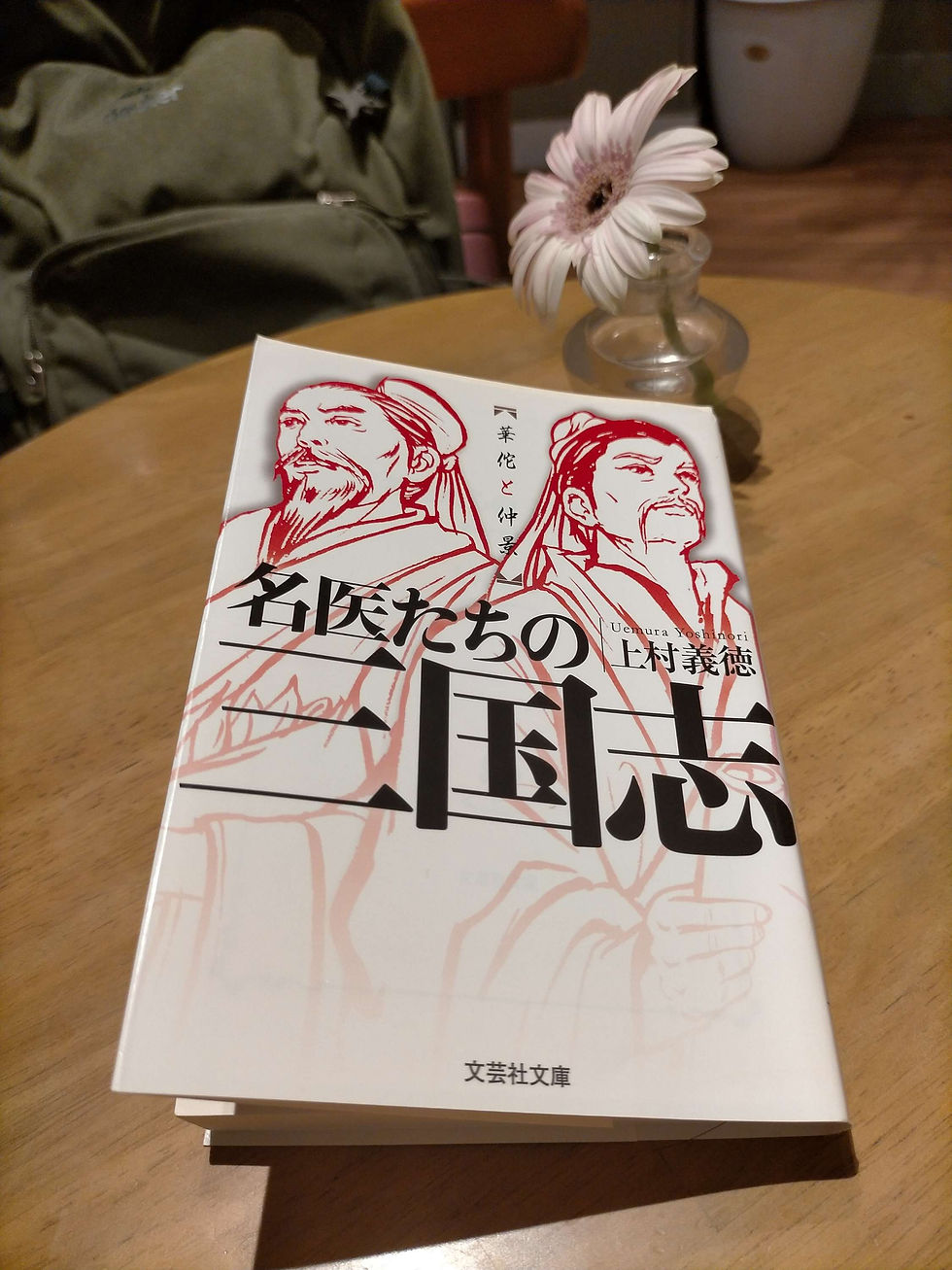


コメント